「初出勤で何をすべきか完全ガイド」|初日から失敗しない5大ステップと成功のための準備リスト
新しい職場への第一歩、それが「初出勤」です。期待とともに「うまくやれるかな」「どんな人たちがいるのだろう」「何を準備しておけばいいのか」といった不安も、多くの人が感じるものです。し...
ジョブジョブ 転職ノウハウ
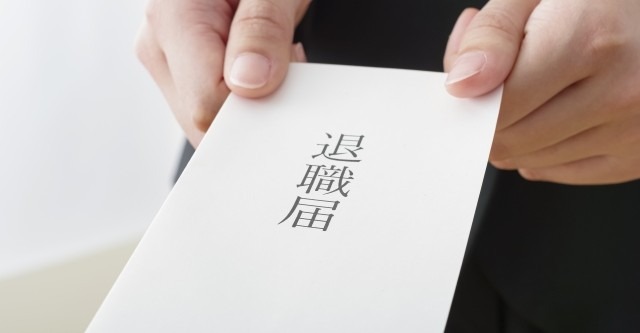
勤め先を円満に退職するためには、退職を切り出すタイミングや、理由の伝え方が非常に重要です。退職交渉の際には、人間関係の悪化や希望通りの退職日が認められないといったトラブルに発展する可能性もあるため、注意すべき点が多くあります。
本記事では、転職を前提とした退職を想定し、退職の意思を会社に伝える適切なタイミングや、引き止められにくい転職理由の伝え方など、スムーズに退職を進めるためのポイントを分かりやすく解説します。
この記事でわかること

退職を決意しても自分の都合でいつでも上司に伝えていいわけではありません。円満退職のためには退職を伝える時期やタイミングを配慮することが重要です。
退職の意思表示を行うタイミングは、会社の就業規則によって異なるため、自社の規則を確認した上で、「退職日の1〜3カ月前」に伝えるのが一般的です。
まずは直属の上司に、「今後についてお話ししたいことがあります。お時間をいただけますか?」と口頭でアポを取るようにしましょう。
最近は、スケジュール管理をカレンダーアプリなどで行っているケースも多いので、その場合は、上司の予定「ご相談」といったタイトルでの予定設定も一般的になりつつあります。
この際、直属の上司以外にアポを取るのはマナー違反です。「重要な話が自分を飛び越えて進められた」と直属の上司の気分を害し、その結果トラブルが起きる可能性があります。そうなれば、円満退職に支障をきたすことになります。
たとえ直属の上司との関係が悪かったとしても組織のルールを無視せず、順を追って適切に相談することが重要です。
退職の意思を伝える際は、忙しい時間帯や重要な商談・会議の準備中など、相手が多忙なタイミングは避けるようにしましょう。退職は会社に一定の影響を与えるため、相手が精神的に余裕のある時に話を切り出す方が、受け入れられやすくなる可能性があります。
また、退職を伝える時期も重要です。
退職者が増える時期は、一般的に年末の12月と年度末の3月です。これは、退職を年度の区切りに合わせることで、社内外の引き継ぎ作業がスムーズに進むためです。
退職のタイミングとして避けるべきなのは“繁忙期”。忙しい時期に「実は来月をもって退職を考えているのですが……」と言っても、忙しいからと話を聞いてもらえない可能性があります。
そのため、上司が時間を取れる余裕があり、気持ちに余裕がある“閑散期”を選んで退職を伝えるのがベストです。
また、大きなプロジェクトが進行中や人事異動後に退職を伝えるのは避けた方が良いです。大きな責任を引き受けた後では辞めにくくなり、引き継ぎも難しくなります。
プロジェクトが終了した後や人事異動の内示が出た直後は、比較的引き継ぎがしやすいため、退職を伝えるには理想的なタイミングと言えます。
転職先が決まっている場合、応募先の企業から内定通知書を受け取り、正式に入社を承諾した後に退職の意思を伝えるようにしましょう。内定通知書が送られ、求職者が入社日や年収など重要な条件を確認したうえで就業する意思を示すことで、労働契約上の「内定」が成立します。単に内定通知書が送られてきただけでは、契約が確定したとは言えず、取り消しのリスクが残ります。
また、口頭で「内定です」と伝えられた場合も注意が必要です。採用の承認がまだ得られていないこともあるため、必ず「書面」で内定通知を受け取るように企業に依頼しましょう。

上司に退職を伝える予定を設定したら、その場で何を伝えるかを整理しておきましょう。
まずは、退職の意志をしっかり伝えることが大切です。
とはいえ、「誰が何と言おうと辞めます」「○月○日までに絶対に辞めます」といった、強硬な言い方や一方的な断言は避けましょう。上司の気分を害さないよう、配慮が必要です。
また、退職理由もきちんと説明したうえで、上司の反応を見ながら、希望する退職日や担当業務の状況について話を進めていくようにしましょう。
退職理由はポジティブな形で伝えるよう心がけましょう。「今後はこの分野でこういった仕事をしていきたい」という自分の気持ちを正直に伝え、退職の時期については「○月までに退職を考えています」と、会社に相談するような表現で伝えるのが理想的です。
退職の原因が何であれ、円満に退職するためには、まず「お世話になりました」と上司や会社への感謝の気持ちを伝え、丁寧かつ冷静に退職の意向を表明することが大切です。
特に「会社への不満」を直接伝えることは避けましょう。上司との関係が悪化する恐れや、場合によっては退職を引き留める材料として使われることもあります。退職は円満に進めることが重要なので、言い方には十分に配慮しましょう。
もし退職の伝え方に不安があり、転職時に人材紹介を利用している場合は、キャリアアドバイザーに相談するのも一つの方法です。キャリアアドバイザーが「上司への退職の伝え方」や「円満退職に向けた交渉方法」をサポートしてくれることがあります。転職活動を始める予定の方は、一度キャリアアドバイザーに相談してみると良いでしょう。
上司に退職の意思と理由を伝え合意を得られてから、同僚や取引先など関係者に退職についてのお知らせをしましょう。
退職日が正式に決まった時点で、まずは上司と相談のうえ、同僚や後輩に伝えるようにしましょう。退職の意思を周囲に伝える前に、上司に報告しないと、現場が混乱したり、うわさが先に広まってしまうなど、トラブルの原因になります。
特に後任者や取引先への通知は、業務に直接関わるため慎重に行う必要があります。上司としっかり話し合い、引き継ぎの計画が整った段階で、チーム全体が集まる場で伝える、または取引先にはプロジェクトの区切りを見計らって知らせるなど、細かく打ち合わせを行い、自分だけで決めないようにしましょう。
また、取引先など社外に退職を伝えるタイミングは、後任が決定した時点が一般的です。退職の連絡方法については、退職メールを送るか、直接訪問して挨拶するかを、上司や先輩と相談して決めるとよいでしょう。
社内外問わず、必要な引き継ぎは確実に行い、感謝の気持ちを伝えることを忘れず、周囲との信頼関係を損なわないよう十分に配慮しましょう。
できる限り直接ご挨拶に伺うのが理想ですが、それが難しい場合は、メールや挨拶状でご連絡を差し上げましょう。
1. メールでご挨拶する場合
メールを用いる際は、これまでのご厚情への感謝をお伝えするとともに、後任者の紹介や引継ぎについても簡潔に触れましょう。直接訪問の予定がある場合でも、事前にメールでご連絡・日程調整を行っておくとスムーズです。
2. 直接ご訪問する場合
可能であれば後任者と共に訪問し、引継ぎと顔合わせを同時に行うのが望ましいです。もし後任者の都合が合わない場合は、先にご挨拶に伺い、後任者の紹介と引継ぎの概要をお伝えしましょう。お取引先にご安心いただけるよう、丁寧な対応を心がけてください。
3. 挨拶状を送る場合
訪問やメールでのご挨拶が難しい場合には、挨拶状の送付もひとつの方法です。特に目上の方や、これまで特別にお世話になった方、手書きの文化を大切にされている方には、丁寧な印象を与えることができます。
取引先へ退職のご挨拶をする際には、以下の3点を必ずお伝えするよう心がけましょう。
1.退職日について
退職日が決まっている場合は、正確な日付を明記しましょう。特に注意が必要なのは、退職日と最終出社日が異なるケースです。有給休暇の消化などで出社が前倒しになる場合には、最終出社日についてもあわせてお伝えすると丁寧です。
2.後任者と業務引き継ぎについて
後任者の氏名と役職などを紹介し、業務の引継ぎがスムーズに進んでいることを伝えましょう。取引先に安心していただけるよう、自分自身が責任をもって後任と引き継ぎを行っていること、必要な情報共有がなされていることを示すことが大切です。
3.感謝の気持ちを伝える
取引の期間に関わらず、これまでお世話になった感謝の気持ちをしっかりと伝えましょう。たとえば「短い間ではございましたが」「〇年間にわたり大変お世話になりました」など、関係性に応じた表現を選ぶと、より誠意が伝わります。
「転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部」は、医療、介護、保育の求人サイト「ジョブジョブ」の運営メンバーによる記事編集部門です。医療・介護・保育・福祉・美容・ヘルスケアの仕事に関わる方に向けた、今後のキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。

新しい職場への第一歩、それが「初出勤」です。期待とともに「うまくやれるかな」「どんな人たちがいるのだろう」「何を準備しておけばいいのか」といった不安も、多くの人が感じるものです。し...

面接では、長所や短所を質問されることがよくありますが、「自分の長所がうまく伝わらない」「短所をどう答えればよいかわからない」と悩む人も多いでしょう。 この記事では、面接で自分...
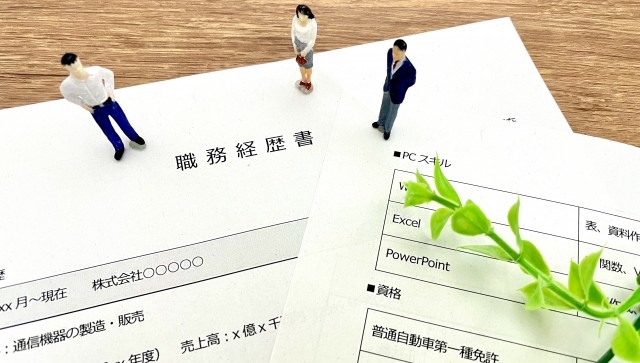
転職活動に欠かせない「職務経歴書」。しかし、いざ書こうと思っても「何をどう書けばいいの?」「履歴書とはどう違うの?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。 実は、職務経...

履歴書とは、個人の基本情報や学歴、職歴、資格などを簡潔にまとめた書類で、主に就職活動や転職活動で企業に提出する書類です。採用担当者に情報を正しく伝えつつ好印象ももってもらうための採...

初めての転職活動では、「どうやって仕事を探せばいいのか」「どんな企業を選べばいいのか」と戸惑う方も多いはず。ここでは、応募先選びのポイントや仕事の探し方について、役立つ情報をわかり...

一般的に、転職活動の期間は3〜6ヶ月ほどが目安とされています。ただし、そのスピードは人それぞれ。実際のところ、転職活動のポイントをしっかり押さえておけば、1ヶ月ほどの短期集中型でも...

薬剤師として転職・就職を考えたとき、多くの方がまず利用を検討するのが「薬剤師専門の求人サイト」です。しかし、実際に検索してみると、求人数が多いサイト、派遣・パートに強いサイト、病院...

歯科衛生士として働いていると、「今の職場より働きやすい医院があるのでは?」「もっと休みが多くて、給与が高い医院を探したい」など、転職について一度は考えるものです。しかし、いざ求人を...