薬剤師 正社員とパートどっちがいい?働き方比較
「薬剤師として働くなら正社員とパート、どちらが自分に合っているのだろう?」 薬剤師は国家資格職であり、比較的高収入が期待できる一方で、働き方の選択肢も豊富です。調剤薬局・ドラ...
ジョブジョブ 転職ノウハウ

高齢化が進む日本社会において、介護の専門職である「ケアマネジャー(介護支援専門員)」の需要が急速に高まっています。介護サービスを受ける方と介護事業者との橋渡し役として、重要なポジションを担うケアマネジャーは、福祉・医療・介護の現場において欠かせない存在です。本記事では、ケアマネジャーの基本的な仕事内容から、必要な資格、年収事情、転職動向、今後の展望までをわかりやすく解説します。
目次
ケアマネジャー(正式名称:介護支援専門員)は、要介護者やその家族の立場に立ち、最適な介護サービスをコーディネートする専門職です。介護保険制度において要となる存在であり、「介護の相談役」かつ「サービスの設計者」とも言えます。
少子高齢化が進行する中で、介護を必要とする高齢者は年々増加しています。一方で、家族だけでは介護を担うことが難しいケースも多く、介護サービスの専門的な知識を持つ人材が不可欠となっています。ケアマネジャーは、そうした介護現場において「利用者のニーズに合わせたケアをデザインし、継続的にサポートする」役割を担っています。
ケアマネジャーの仕事は、単独では成り立ちません。医師、看護師、理学療法士、社会福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)など、さまざまな専門職と連携しながら、一人の利用者を多角的に支えていく必要があります。そのため、**「調整力」「交渉力」「説明力」**といったソフトスキルが非常に重視されます。
介護に関する知識が少ない利用者や家族にとって、ケアマネジャーは頼れる相談窓口でもあります。適切な情報提供と提案を通じて、利用者の生活の質(QOL)向上に直結する支援が可能です。
ケアマネジャーの仕事は、介護が必要な人の生活を全体的に支えるための設計・調整業務です。単に介護サービスを紹介するだけでなく、利用者の身体的・精神的状態や家庭の事情、地域資源を総合的に判断し、最適なケアプランを立て、それを実行・検証していくことが求められます。以下に具体的な業務内容を細かく紹介します。
ケアマネジャーは、要介護認定をまだ受けていない人や更新が必要な人に対し、申請手続きの代行やサポートを行います。市区町村の窓口への申請書類の提出、本人や家族からの聞き取り、主治医意見書の取得支援などが含まれます。
ケアプラン作成の前に、ケアマネジャーは利用者本人や家族への詳細なヒアリングを実施します。これを「アセスメント」と呼び、利用者の生活状況、身体機能、認知機能、家族の支援体制、住環境などを多角的に把握します。
例:入浴が困難 → 入浴介助が必要、または住宅改修を検討
アセスメントを元に、**ケアプラン(介護サービス計画)**を作成します。プランには以下のような内容が含まれます。
ケアプランは必ず利用者・家族の同意を得た上で正式に交付され、サービスが開始されます。
ケアプランを作成したら、関係する事業者や専門職を招いてサービス担当者会議を開催します。ここでは、各事業者がどのように支援するかをすり合わせ、利用者のニーズに応える体制を構築します。
ケアプラン実行後も、ケアマネジャーは各事業者(ヘルパー、デイサービス、訪問看護、福祉用具業者など)との連絡・調整役を担います。利用者の体調変化や家族構成の変化があった場合には、サービス内容の変更や追加依頼を行います。
介護サービスが適切に提供されているかを確認するため、ケアマネジャーは月に1回以上利用者の自宅や施設を訪問し、モニタリングを行います。サービスの質、利用者の満足度、体調の変化などをチェックし、必要に応じてプランの修正を行います。
利用者の状態は常に変化します。たとえば「転倒して骨折した」「認知症が進行した」「家族の支援体制が変わった」といった状況に応じて、再アセスメント→プランの修正が必要になります。
ケアマネジャーは、訪問記録、アセスメントシート、ケアプラン、モニタリング記録など、多くの帳票を正確に作成・管理する必要があります。これらは、行政の監査や給付管理の根拠となる重要な書類です。
介護サービスに対して支払われる介護給付費の管理・請求業務もケアマネジャーの仕事です。利用者が利用したサービス内容に基づき、介護保険事務所へ請求データ(給付管理票)を提出します。
日々の介護に対する不安や疑問、家族間のトラブル、施設入所の希望など、利用者や家族の悩みに対して相談支援を行います。医療や福祉、法律、制度などの幅広い知識が求められます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)になるためには、「ケアマネジャー試験」に合格し、実務研修を修了する必要があります。ただし、誰でも受験できるわけではなく、一定の実務経験や国家資格の保有が必要です。以下に、資格取得までの流れと条件を詳しく説明します。
以下国家資格を持ち、かつ5年以上の実務経験(900日以上)がある人が対象です。
| 職種 | 合格者数 | 割合 |
| 介護福祉士 | 7,389人 | 62.4% |
| 看護師・准看護師 | 1,925人 | 16.3% |
| 社会福祉士 | 948人 | 8.0% |
| 理学療法士 | 613人 | 5.2% |
| 作業療法士 | 253人 | 2.1% |
| 保健師 | 250人 | 2.1% |
| 相談援助業務等従事者 | 271人 | 2.3% |
| その他(医師、薬剤師、栄養士など) | - | - |
※合格者数は延べ人数であり、複数の資格を有する者も含まれます。
ケアマネジャー試験の合格者は、介護福祉士や看護師などの医療・福祉系の国家資格を有する者が大多数を占めています。これは、受験資格としてこれらの職種での実務経験が求められるためです。また、近年では多職種連携が重視されており、理学療法士や作業療法士、保健師など、さまざまな専門職からの受験者も増加傾向にあります。
パターン②:資格がなくても受験できるケース(例外)
法定資格を持っていない場合でも、以下の施設等で相談援助業務を5年以上行っていた方も受験できます。
この場合も、「相談援助業務の内容証明書」などの証明書類を提出する必要があります。
ケアマネ試験は、毎年10月に全国で実施され、合格率はおおむね10〜20%程度と非常に低いことで知られています。試験科目は以下の通りです:
主にマークシート形式で出題され、合格基準は両分野で一定点数以上かつ総得点の6割前後とされています。
試験に合格後は、**実務研修(87時間以上)**を受講します。研修内容は以下のような実践的プログラムです。
この研修を修了することで、初めて「介護支援専門員証」が発行され、ケアマネジャーとしての活動が可能になります。
介護支援専門員証には5年間の有効期限があります。そのため、更新の際には更新研修の受講が必須です。また、現場で一定の業務に従事していなければ、更新できないこともあるため注意が必要です。
ケアマネジャーにはキャリアアップ制度も存在します。その代表が**「主任介護支援専門員」**です。これは、実務経験5年以上のケアマネジャーが所定の研修を受講することで取得可能となり、以下のような役割が期待されます:
主任ケアマネの資格を持っていると、求人でも優遇されやすく、給与も高くなる傾向にあります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の年収は、勤務先の種類や地域、経験年数、資格の有無(主任ケアマネ等)によって大きく異なります。ここでは、平均的な年収データに加え、具体的な年齢別・地域別・資格別の傾向を詳しく見ていきます。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」などのデータをもとにすると、ケアマネジャーの全国平均年収は以下の通りです:
| 区分 | 年収 | 月収 | 賞与(年2回平均) |
| 全国平均 | 約390万円 | 約26~28万円 | 約60~80万円 |
ただしこれはあくまで平均値であり、実際には350万円~500万円の幅であることが多いです。
ケアマネジャーの勤務先によって、給与水準には大きな差があります。以下は主な勤務先別の目安です。
| 勤務先 | 年収目安 | 特徴 |
| 居宅介護支援事業所 | 350万~400万円 | 訪問中心。1人で20〜40名担当することも。 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 380万~420万円 | 施設利用者のケアマネジメント。夜勤は基本なし。 |
| 介護老人保健施設(老健) | 370万~430万円 | 医療と介護の連携重視。多職種チームが多い。 |
| 地域包括支援センター | 400万~480万円 | 公的業務で安定性高。主任ケアマネが求められることも。 |
| 病院(医療機関) | 420万~500万円 | 医療ソーシャルワーカーとの兼務も。退院支援に特化。 |
特に地域包括支援センターや病院勤務のケアマネは給与が高めになる傾向があります。
| 年齢層 | 平均年収 | 傾向 |
| 20代後半 | 320万〜350万円 | 初任給レベル。資格取りたての時期。 |
| 30代 | 350万〜400万円 | 中堅として独り立ち。件数も増える。 |
| 40代 | 400万〜450万円 | 主任ケアマネ取得者が増え、管理職も視野。 |
| 50代以上 | 450万〜500万円超 | 管理職・ベテラン層。地域包括や施設長など |
経験年数が多いほど利用者対応力や書類精度が向上し、給与水準もアップします。
主任介護支援専門員の資格を取得すると、給与が月2万〜5万円ほどアップするケースが多いです。施設によっては手当がつくほか、地域包括支援センターや行政系の求人では、主任ケアマネ資格が必須条件であることもあります。
| 資格 | 平均月収 | 備考 |
| 一般ケアマネ | 26~28万円 | 担当利用者30人前後が平均 |
| 主任ケアマネ | 30~35万円 | 担当+指導・教育・管理業務も |
地域によっても年収差があります。特に**都市部(東京・神奈川・大阪など)**では給与が高めに設定される傾向がありますが、生活コストも高くなるため、手取りベースで考慮する必要があります。
| 地域 | 年収目安 | 特徴 |
| 首都圏(東京・神奈川) | 400万〜470万円 | 求人数多いが業務量も多め |
| 東海・近畿 | 380万〜450万円 | 老健・特養が多くバランス型 |
| 北海道・東北 | 340万〜400万円 | 高齢化率が高く地域需要あり |
| 九州・沖縄 | 330万〜390万円 | 地域差や企業体質により幅が大きい |
ケアマネジャーには基本給のほかに、以下のような手当や報酬制度がある場合もあります。
一部では、居宅介護支援事業所を個人で開設して独立するフリーランスケアマネも増えてきています。報酬は「利用者1人あたりいくら」という定額制で支払われるため、件数を多く持てば高収入も可能です。ただし、事務管理・帳票業務・営業など全て自分で担う必要があるため、ハードルは高めです。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、勤務する施設や機関によって役割や働き方、1日のスケジュール、担当する利用者の数などが大きく異なります。自分に合った働き方を見つけるためにも、各勤務先の特徴を正しく理解しておくことが重要です。
特徴:
働き方のポイント:
こんな人に向いている:
特徴:
働き方のポイント:
こんな人に向いている:
特徴:
働き方のポイント:
こんな人に向いている:
特徴:
働き方のポイント:
こんな人に向いている:
| 勤務先 | 訪問の有無 | 担当人数 | 連携対象 | スケジュール自由度 | 残業傾向 |
| 居宅介護支援事業所 | あり | 30〜40人 | 利用者・家族・事業者 | 高め | やや多い |
| 介護施設 | なし | 30〜100人 | 看護師・介護職 | 中程度 | 比較的少なめ |
| 地域包括支援センター | 場合によりあり | 少なめ | 自治体・地域住民 | 低め | やや多い |
| 病院 | なし | 不定(主に退院支援) | 医師・MSW・家族 | 中程度 | 少なめ |
ケアマネジャーは、利用者や家族、介護・医療・行政の関係者と連携しながら最適なケアプランを立案・実行する重要な職種です。そのため、専門知識だけでなく対人関係能力・調整力・問題解決力など、幅広いスキルが求められます。ここでは、ケアマネジャーに求められる主なスキルと、それに適した人物像について詳しく解説します。
ケアマネジャーの基本は「人との対話」です。利用者本人や家族の不安・希望・困りごとを丁寧に聴き取り、信頼関係を築くことが重要です。
具体的なシーン:
こんな人に向いている:
ケアプランの土台となる「アセスメント(課題分析)」には、表面に出てこない情報を引き出す力が必要です。何気ない言動や生活環境から、潜在的なニーズやリスクを見抜く力が求められます。
重要な視点:
ケアマネジャーは「調整役」であり、さまざまな立場の人をつなぐハブ的存在です。時には、医療職と介護職、利用者と事業者、家族同士の間に立って意見を調整する必要があります。
求められる力:
介護保険法をはじめ、関連制度(医療保険、障害福祉、生活保護、成年後見制度など)への幅広い理解が不可欠です。また、要介護認定のしくみ、サービスの種類や報酬の仕組みなども熟知している必要があります。
知っておくべき制度:
ケアマネジャーは、ケアプランをはじめ、アセスメントシート、モニタリング記録、給付管理票など、書類作成が非常に多い職種です。パソコンや介護ソフトの操作スキルも実務において必須となります。
求められるスキル:
ケアマネジャーは、突発的な対応やクレーム処理に追われることもあります。限られた時間内で優先順位をつけ、冷静に対応する力とメンタルの安定性が必要です。
試される場面:
ケアマネジャーは、個人情報を扱い、利用者の生活を左右する計画を立てる職種です。そのため、公正・中立な視点と高い倫理観が求められます。
具体例:
高齢化の進行と介護保険制度の改正を背景に、ケアマネジャーのニーズは全国的に高まっています。しかし、資格保有者の高齢化や離職率の上昇、業務の多忙さから、慢性的な人材不足が続いており、転職市場では「売り手市場」と言える状況です。
この章では、ケアマネジャーの転職動向や人気求人の傾向、転職を成功させるためのポイントを詳しく解説します。
そのため、経験者・主任ケアマネ資格保有者は特に歓迎される傾向にあります。
| 勤務先 | 求人数の傾向 |
| 居宅介護支援事業所 | 常に人材を募集。働き方の自由度が魅力。 |
| 介護施設(特養・老健など) | 利用者数が多く、配置基準により常時求人あり。 |
| 地域包括支援センター | 主任ケアマネの取得者を中心に求人多数。 |
都市部は施設数が多く、在宅介護支援の需要も高いため、常に求人が掲載されている状態です。
求職者が重視する条件は年々変化していますが、現在は以下のような条件を掲げる求人が人気です。
| 条件 | 求人側の対応 |
| 年間休日120日以上 | 働き方改革の影響で増加中 |
| 土日祝休み | 居宅系で増加傾向 |
| 在宅勤務可 | 一部の事業所で導入、報告や記録業務を在宅で |
| 残業少なめ | 月10時間以下を明示する求人が多い |
| 主任ケアマネ歓迎 | 管理職登用・手当付きの求人が多い |
また、有資格者で未経験OKとする求人も増えており、資格は取ったが実務経験のない人へのチャンスも広がっています。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護の現場で利用者一人ひとりの人生に深く関わる責任ある職業です。その分、やりがいも大きい一方で、業務量や精神的負担の多さから「大変」と感じる側面も少なくありません。ここでは、ケアマネジャーの仕事の魅力(やりがい)と、現場で感じやすい困難(大変なこと)を具体的に紹介します。
ケアマネジャーは、利用者本人やその家族から生活全体を相談される「身近な専門家」です。長期的に関わることで、利用者の安心や生活の質(QOL)の向上を実感でき、「○○さんが担当でよかった」と感謝の言葉をもらえることは大きなやりがいです。
「あなただから相談できた」
「おかげで家で安心して暮らせています」
といった言葉は、何よりのモチベーションになります。
ケアマネは、多職種と連携しながら一人の利用者の生活を支える「チームケアの司令塔」のような存在です。医師、看護師、リハビリ職、訪問介護員、行政担当者などと連携してケアが円滑に回った時、大きな達成感があります。
例えば、うつ状態で寝たきりだった高齢者が、デイサービスの利用で笑顔を取り戻し、外出するようになった——。そんな変化を近くで見守れるのはケアマネだけです。自分の提案が生活の改善につながる体験は、何物にも代えがたい充実感をもたらします。
ケアマネは、制度・医療・福祉・介護・人間関係に精通する多能工的な職種です。制度改正や新しい地域資源への対応を通じて常に成長できる環境があり、「知識が人の役に立つ」ことを実感しやすい職種です。
ケアマネジャーの仕事は「人と会うだけ」ではありません。ケアプラン、アセスメント、モニタリング、給付管理など、毎月提出すべき書類や帳票が膨大です。
訪問先で利用者の状態が急変したり、家族から深夜に連絡が入ることもあります。緊急性が高くない場合でも、「何とかしてほしい」という要望に応える必要があり、プライベートとの線引きが難しいこともあります。
ケアマネジャーは利用者と家族、介護サービス事業者、医療職、行政などさまざまな立場の人々の間に立つ調整役です。全員の要望を満たすことが難しい中で、冷静な判断と中立性が常に求められます。
例:利用者は「もっとサービスを増やしたい」
→ しかし家族は「費用が負担」と反対、制度上も上限あり
このような時に「誰のためのケアか」を見失わない判断力が必要です。
制度改正や報酬基準の変更、サービス新設など、介護保険制度は数年おきに見直されます。ケアマネはその都度対応が求められるため、常に情報をアップデートする努力が欠かせません。自主的な研修参加や勉強会への出席が必要です。
特に居宅系のケアマネは一人職場も多く、上司や同僚に相談しにくい環境になることもあります。また、外回りと書類業務で物理的に人と関わる時間が限られることも。
ケアマネジャーは今後も重要性が増す職種です。高齢化がさらに進行する日本において、介護と医療、地域との連携を担うコーディネーターとしての役割は、今後の地域包括ケアシステムの中核を担う存在となっていくでしょう。
以下では、ケアマネジャーを取り巻く将来の需要の見通しと、資格取得後のキャリアの広がり方(キャリアパス)について解説します。
このような背景から、ケアマネジャーの活躍の場はさらに拡大する見込みです。
ケアマネジャーは、現場のスペシャリストとして経験を積むだけでなく、管理職・指導職・地域貢献職へとキャリアを広げることが可能です。以下に代表的なキャリアパスを紹介します。
Q. ケアマネジャーは何歳からでもなれる?
A. 受験資格を満たせば何歳でも可能です。実際、40代・50代から資格取得する方も多いです。
Q. ケアマネ試験は難しい?
A. 合格率は約10〜20%と低めですが、対策をしっかり行えば合格可能です。
Q. ケアマネに向いていない人は?
A. 一人で抱え込みやすい、チームでの連携が苦手な方には不向きかもしれません。
ケアマネジャーは、高齢社会の日本においてますます重要性を増す仕事です。社会貢献性が高く、専門性とやりがいのある職種として、今後も注目される存在となるでしょう。転職やキャリアアップを考えている方は、ぜひ自分に合った働き方を見つけてください。
厚生労働省のHPでもケアマネージャーの紹介PDFがありますので参考にしてみてください。
「転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部」は、医療、介護、保育の求人サイト「ジョブジョブ」の運営メンバーによる記事編集部門です。医療・介護・保育・福祉・美容・ヘルスケアの仕事に関わる方に向けた、今後のキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。

「薬剤師として働くなら正社員とパート、どちらが自分に合っているのだろう?」 薬剤師は国家資格職であり、比較的高収入が期待できる一方で、働き方の選択肢も豊富です。調剤薬局・ドラ...

「30代になってから介護職で転職しても、年収は上がるのだろうか」これは、私自身が転職を考え始めたとき、何度も自分に問いかけていた疑問です。 介護職はやりがいのある仕事である一...
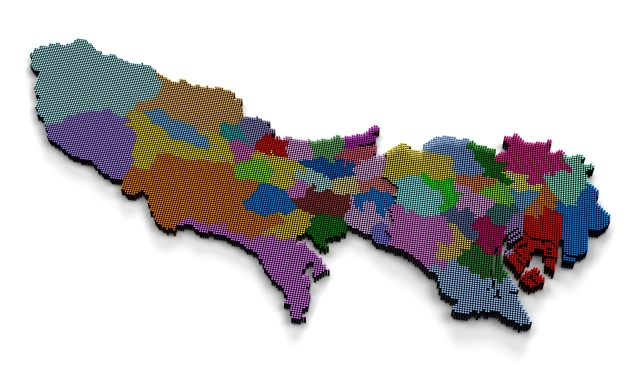
東京都は日本最大級の医療集積地であり、看護師求人の数・種類・選択肢の多さは全国トップクラスです。大学病院や高度急性期病院が集中する都心部、地域医療を支える総合病院が多い城東・城北エ...

「保育士はやりがいはあるけれど、年収がなかなか上がらない」そう感じながら働いている方は少なくありません。実際、保育士は社会的に重要な役割を担っている一方で、給与水準の低さや昇給のし...

介護業界で仕事を探していると、「どんな求人が人気なのか」「応募が集まりやすい条件は何か」が気になる方も多いのではないでしょうか。実際、介護職の求人は数多く存在しますが、求職者が検索...

2026年を迎え、看護師の採用市場はこれまで以上に地域差・職種差が鮮明になっています。高齢化の進行、在宅医療の拡大、病床機能の再編、そしてコロナ禍以降の離職・復職の波—こうした複数...

医療現場で患者やその家族の「心の支え」となり、社会的な課題の解決をサポートする専門職、それが「医療ソーシャルワーカー(MSW)」です。高齢化や医療の複雑化が進む中、MSWの重要性は...

「サービス管理責任者(通称:サビ管)」という言葉を聞いたことがあっても、「実際にはどんな仕事?」「資格は必要?」「給料はどのくらい?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。 ...

福祉業界でキャリアアップを目指す方の中で、近年注目を集めている資格が「サービス管理責任者(サビ管)」です。障害福祉サービス事業所では必ず配置が求められる国家資格に準ずる専門職であり...

介護の仕事に就くうえで、「どんな資格を取ればいいの?」「未経験でも取れる資格はある?」と悩む方は多いでしょう。介護業界は資格の種類が多く、キャリアステップや働き方によって選ぶべき資...